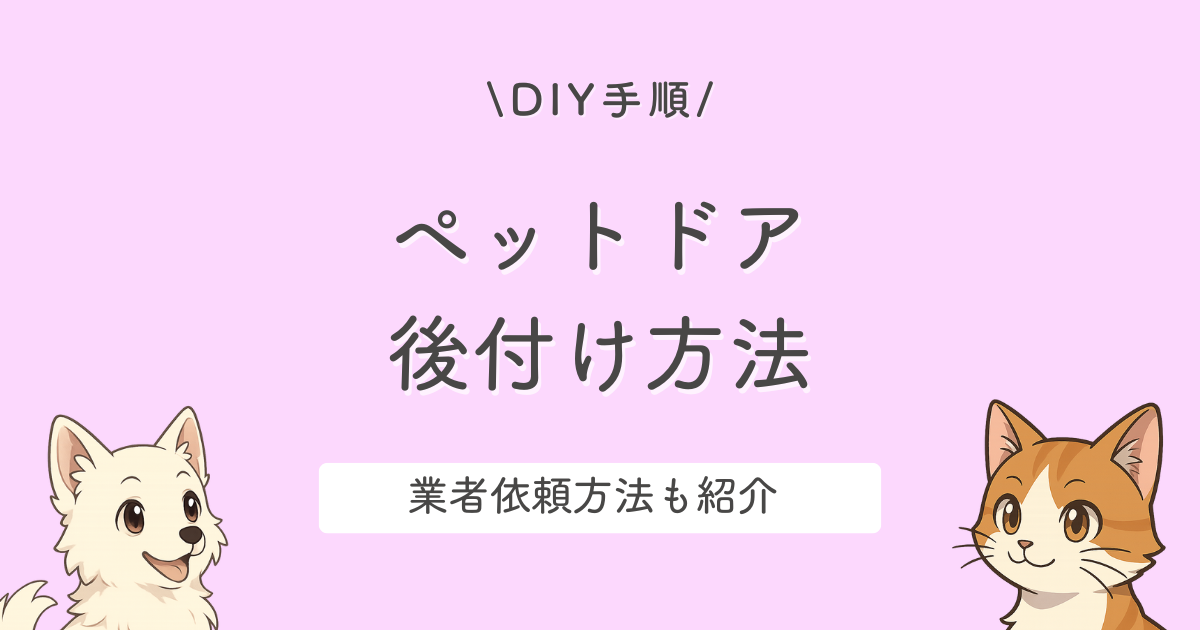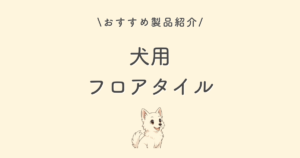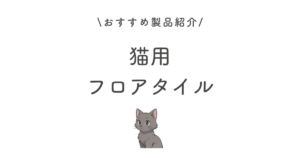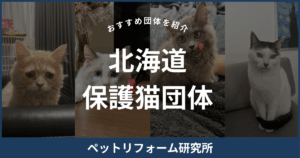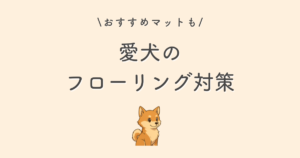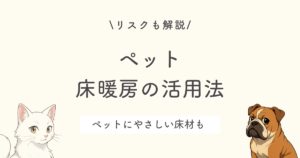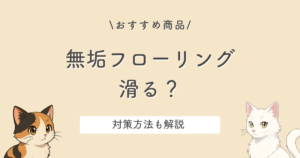ペットが自由に出入りできる環境を整えるために、「ペットドアの後付け」を検討する飼い主が増えています。外出時に毎回ドアを開けてあげる手間を省きたい、室内の移動をスムーズにしてストレスを減らしたい――そんな願いを叶えるのがペットドアの導入です。
しかし、いざ取り付けようとすると「DIYでできるのか」「失敗したらドアが台無しにならないか」「業者に頼むならいくらかかるのか」など、疑問や不安が出てくるものです。本記事では、初心者にもわかりやすいように、DIYによる取り付け手順や必要な道具、そして業者に依頼する際の費用相場や選び方まで詳しく解説します。
この記事を読むことで、自分に合った方法を見極め、自信を持ってペットドアの後付けに取り組めるようになります。
このページでわかること
- ペットドアを後付けするメリットと注意点
- DIYで取り付ける手順と必要な道具
- 業者に依頼する際の費用相場と選び方
- ドア材質やペットのサイズに応じた設置のポイント
- 設置後のトレーニング方法とメンテナンス方法
ペットドアを後付けするメリット

ペットドアを後から取り付けることで、飼い主とペットの双方に多くの利点があります。移動の自由度が増すことでペットのストレスが減り、同時に飼い主の手間も軽減されるため、生活の質を総合的に高めることができます。
- ペットが自力で移動できるようになり、ストレスが減る
- ドアの開閉をしなくて済むため、飼い主の負担が軽くなる
- 留守中でもペットの行動が制限されず安心
- 冷暖房効率や防犯性に配慮された高機能モデルも選べる
これらの効果は、日々の暮らしの中で少しずつ実感できるようになります。
ペットの自由な移動を実現
ペットにとって、空間を自由に行き来できることは快適な生活に直結します。特に好奇心旺盛な猫や、外でトイレをする習慣がある犬にとっては、移動の自由があることで不安やストレスが大幅に減ります。
- 室内の好きな場所に移動し、気分に応じた居場所を確保
- 飼い主の外出中でも外のトイレに行ける
- 夜間の移動やトイレも自由に行える
このように、行動の自由はペットにとって大きな安心材料となります。
飼い主の手間軽減と生活の質向上
ペットの行動に合わせてドアを開け閉めすることは、思いのほか手間がかかる作業です。特に忙しい時間帯や、就寝中・在宅勤務中などに頻繁に呼ばれると、集中力や睡眠の質にまで影響が出ます。
飼る利便性だけでなく、生活全体の快適さにもつながります。

DIYでのペットドア取り付け方法
自分でペットドアを取り付けたいと考える飼い主にとって、手順をしっかり理解することが成功の鍵となります。基本的な工具と計画があれば、初めてでも比較的スムーズに作業を進めることができます。
必要な道具と材料の準備
まずは、作業に必要な道具と材料を準備します。適切な工具がそろっていないと、作業中に中断したり、思わぬトラブルを招くことがあります。
使用頻度の高い道具・材料を一覧でまとめると、以下のようになります。
| 道具・材料 | 用途 |
|---|---|
| 電動ドリル | 切断前の下穴あけに使用 |
| ジグソー | ドアを切断する際に使用 |
| ドライバー | ネジ留め作業全般に使用 |
| メジャー・水平器 | 取り付け位置を正確に測るため |
| 型紙(テンプレート) | ペットドア本体に付属していることが多い |
| ペットドア本体 | 取り付け対象の製品 |
このほか、養生テープや木くずを処理するための掃除道具も用意しておくと安心です。
取り付け位置の決定とマーキング
に行うのが、ペットドアの設置位置を決める作業です。位置決めは、見た目だけでなく機能性にも大きく関わります。
以下の点に注意して位置を決めましょう。
- ペットの体高に合わせて設置
↳地面からペットのお腹の高さが基準 - ドアの中央に左右対称で設置
↳見た目が整い、安定性も確保される - 開閉の邪魔にならない位置を選定
↳ドアノブや家具との干渉を避ける
設置場所を決めたら、付属の型紙を使ってマーキングします。型紙がない場合は、ペットドア本体を一度当てて線を引くのが有効です。
ドアの切断と整形作業
丁寧に進めましょう。切断作業の流れは以下のとおりです。
- 四隅にドリルで下穴を開ける
- 下穴からジグソーを入れて切断開始
- 線に沿ってゆっくりカット
切断後は、断面にバリ(ささくれ)が出るので、紙やすりなどでなめらかに整えてください。断面が不安定だと、ペットドアの設置がうまくいかない原因になります。
ペットドアの本体取り付け
最後に、ペットドア本体を取り付けて作業完了です。このステップも、正確な取り付けが求められます。基本的な取り付け手順は次の通りです。
- 外枠と内枠を合わせて仮固定
- ドライバーでネジ止め(付属ネジを使用)
- 開閉がスムーズか確認
- 必要に応じてパッキンやシーリング材で補強
取り付け後は、扉の動作確認と、開閉に違和感がないかを必ずチェックしましょう。歪みやぐらつきがある場合は、一度ネジを緩めて微調整することが大切です。
ペットドアの後付け時の注意点と対処法

ペットドアの後付けは便利な反面、ドアの種類や住環境によって注意すべき点があります。特に、ドア材質との相性や賃貸物件での制限、ペットのサイズに合った選定を怠ると、トラブルの原因になります。
ドア材質別の注意点
ドアの素材によって、切断しやすさや耐久性が異なり、適切な施工方法も変わってきます。素材に合った方法で施工しなければ、割れや変形などのリスクが高まります。
主なドア材質と注意点を表にまとめました。
| ドアの材質 | 特徴と注意点 |
|---|---|
| 木製 | 加工しやすいが、水分による変形に注意 |
| アルミ製 | 切断には専用の刃が必要で、バリが出やすい |
| スチール製 | 切断が困難で、DIYには不向き |
| 中空樹脂(ハニカム) | 断熱性が高いが、中が空洞なので補強が必要 |
不安な場合は、材質に応じた施工が可能な業者に相談するのが無難です。
賃貸物件での設置方法
賃貸住宅では、原状回復の義務があるため、ドアの加工が制限されることがほとんどです。とはいえ、工夫次第で設置することは可能です。
賃貸で検討すべき対応策は以下の通りです。
- 既存ドアを保管し、退去時に戻せるようにする
↳ホームセンターで同型のドアを購入し、加工用として使う - 工具不要の「突っ張り型ペットドア」を選ぶ
↳壁やドアを傷つけずに設置可能 - 管理会社に事前相談
↳許可を取っておけばトラブルを防げる
ドア本体を交換して加工する方法は、最も確実でリスクが少ない方法です。
ペットのサイズに合ったドアの選び方
ペットドア選びでもっとも重要なのが、サイズの適合です。小さすぎると通れず、大きすぎると防犯性や断熱性が損なわれる可能性があります。
適切なサイズ選びのポイントをまとめました。
- ペットの肩幅+5cmを目安に開口部を選ぶ
↳スムーズな通行を確保 - 地面からお腹の高さを基準に取り付け位置を調整
↳段差やジャンプを防ぐ - 成長を考慮して余裕のあるサイズを選ぶ
↳特に子犬・子猫の場合は成長後を想定
また、多頭飼いしている家庭では、最も大きいペットに合わせて選ぶのが基本です。
まとめ
この記事では、ペットドアを後付けする方法として、DIYの具体的な手順から、業者に依頼する際のポイント、設置時の注意点や対処法までを幅広く解説しました。
自分で取り付ける場合でも、基本的な道具と正確な作業を心がければ、初めてでも十分に対応可能です。一方で、材質や設置環境に不安がある場合は、無理をせず専門業者への依頼を検討するのが安心です。
また、設置するだけでなく、ペットのサイズや性格に合った製品選びや、慣れさせるためのトレーニングも大切です。特に賃貸物件の場合は、原状回復の方法を想定した施工が求められるため、導入前の下調べが重要になります。